法華経 第一章 『 迹 門 』
「諸佛世尊は唯(ただ)一大事の因縁を以ての故にのみ世に出現したもう」
『法華経方便品第二』に示されるこの言葉は、仏はただ一つの大事をなす為だけにこの世に現れるという意味です。これを「一大事の因縁」といいます。「一大事」とは仏自らが悟った「智慧」を衆生にも開かせ、示し、悟らせ、そしてその境地に入らせることで、これを開示悟入の「四仏知見」といいます。「一大事」について大聖人様は、『御義口伝巻上』の中で(御書P.717)、
「一とは中諦・大とは空諦・事とは仮諦なり此の円融の三諦は何物ぞ所謂南無妙法蓮華経是なり」
と仰せになり、空・仮・中の三諦が円融することが南無妙法蓮華経であると御指南あそばされています。ではその「円融の三諦」とはどういうことなのかをお話していきます。まず一念三千の法門と空・仮・中の三諦の関係についてですが、『一念三千法門』の中で大聖人様は次のように仰せです(P.413)。
「百界と顕れたる色相は皆総て仮の義なれば仮諦の一なり 千如は総て空の義なれば空諦の一なり 三千世間は総じて法身の義なれば中道の一なり、法門多しと雖も但三諦なり此の三諦を三身如来とも三徳究竟とも申すなり」
一念三千の法門は、仮諦で捉えた一念三千と、空諦に転じた一念三千と、中諦に即した一念三千によって成り立ちます。創価学会や日蓮正宗では「一念三千の法門」を説明する際、必ず用いるのが「十界論」です。十界論は過去世の行いによってもたらされる現実社会の十界の差別の色相を説いたもので、上の御文の「百界と顕れたる色相は皆総て仮の義なれば仮諦の一なり」にあたります。日蓮正宗の教学では「開会」の意味を誤って解釈してしまっている為、学会員さんや日蓮正宗の法華講員さん達は、法華経以前に説かれた「空」および「無我・無自性」についての知識が大きく欠落しています。
法華経以前の教えは全て法華経に集約されているので学ぶ必要はないと教えられているからです。ですから爾前経の中で説かれる「空理」や、それに関わる「無我・無自性」といった大事な教学の理解が出来ていません。その結果、日蓮正宗や創価学会の教学では仮諦で捉えた一念三千の解釈にとどまってしまい、その先にある空諦、中諦の悟りにまで至っておりません。
法華経迹門の中で示される「開会」は、三乗に開いて説いた教えを一仏乗に顕す「開三顕一」のことで、三乗の教えとは、声聞乗、縁覚乗、菩薩乗のそれぞれの境涯に即して説かれた三種の教えを指し、「乗」は乗り物の意で,衆生を迷いの世界から,悟りへと運ぶことを意味します。「顕一」とは仏界を顕すと言う事で、簡単に言えば、「三乗を説いて仏の道へと導く」と言う事です。
釈迦は、『法華経』の方便品の中で十如是を説いて、ほぼ要略して「開三顕一」を説きます。これを「略開三顕一」と言うのですが、これに対して方便品第二の後半から授学無学人記品第九にわたって法理や譬喩、因縁を通して広く三乗を開いて「開三顕一」が説かれます。これを「広開三顕一」と言います。
法説周・譬説周・因縁説周の三周の説法によって明かされた「広開三顕一」は、上根の舎利弗が法説周によって未来成仏の記別を受け、その後の、譬説周・因縁説周によって中根・下根の二乗の成仏が説き明かされます。
法華経の前半部にあたる迹門は、このように「開三顕一」の説法が中心となって二乗作仏が説かれています。舎利弗をはじめとする声聞の弟子達は三周の説法を聞いて、今まで実践してきた声聞乗、縁覚乗、菩薩乗の修行が全て一仏乗に集約されることを悟って成仏していきます。
日蓮正宗では、この「開三顕一」を便品第二の「正直捨方便」の一節にもとづいて、方便として説かれた三乗の教えは捨てるべき教えであると解釈しています。ですから爾前経の中で説かれる空理や、それに関わる無我・無自性といった教学を学ぶ必要の無いものと捉えています。空・仮・中を説く三諦論は「空」を学んではじめて理解できる法論で、「空」を知らない学会員さんや法華講員さん達が空・仮・中の三諦を正しく語れるはずもありません。実際に創価学会第二代会長の戸田会長の「三諦論」をみてみましょう。
戸田会長の三諦論
『戸田城聖全集 第二巻 質問会編』より「空仮中の三諦」
(「ブログで読める戸田城聖全集 第二巻
質問会編
(創価学会)SGI」H.P.より)
◇◇◇◇◇
空仮中の三諦などというと、ちょっとわからないでしょうが、これは空諦、中諦、仮諦と、仏法哲学において、この世の中の実相がどういうものか、われわれの命がどういうものであるか、ということを考える考え方を根幹として、「空仮中の三諦」というのがあるのです。これは、天台大師の師匠である南岳大師が考えだした哲理なのです。
このなかで、私がこうして生きているのは、仮の実体です。私はこのままかといってもそうはいかないでしょう。もう十年もたって、私がもし生きて六十七歳にもなったら「先生、ずいぶん変わりましたね」ということになるでしょう。
しかしこれだって、私は二十歳のころは美男子だったのです。そしたらその美男子と、いまのように美男子でないのと、どちらがほんとうなのか、それはどちらもほんとうです。ですから仮の実体というのです。いまのは仮の実体としか見えません。これを仮諦といいます。
空諦とは、あるといえばある、ないといえばない、こういうところのものを有無にかかわらず、真の実在をば空諦というのです。私の生命も空諦です。おまえはおじいさんの時があるといえば、それはいまはないでしょう。
たしかにおじいさんではない、私は青年です。しかしおまえは赤ん坊の時はなかったかといえば、なかったのではない、あったのです。そうなると生命は空であります。それであって戸田城聖は中道法相(ちゅうどうほっそう)、戸田城聖は厳然として永遠にそなわっている、これが中諦であります。
◇◇◇◇◇
戸田会長は空仮中の三諦は、「生命の考え方」であると前置きし、生命は常に変化するものであって今一瞬の姿は仮の姿であり真実の姿は空である。しかし戸田城聖という人間は現実に実在している。仮でもあり空でもあるから中道なのであると説明されています。
空仮中の三諦はそのような「生命の考え方」などではありません。また「生命のあり方」でもありません。苦しみや悩みといった煩悩をいかに悟りに転換していくかという「煩悩即菩提の法門」を説く教えです。
次に第三代会長の池田会長の三諦論をみてみましょう。
池田会長の三諦論
(池田会長全集5 御義口伝講義より)
◇◇◇◇◇
空諦 仮諦 中道
空諦は事物の性分、
仮諦は事物のあらわれた姿・形
中道は事物の本質
人間生命でいえば、
その人の性分・心は 空諦
姿・形は 仮諦
生命は中道
たとえば水。お湯になろうが、氷になろうが 水蒸気になろうが そのものの本質には変わりがない。H2Оそれ自体は、中道であり、法身といえよう。水蒸気となり、あるいは氷となり、あるいは冷水となる。その姿・形は仮諦であり、応身である。
また、水は、表面張力があり、あるいは溶解力があり、そしてまた、零度以下では氷となり百度以上では水蒸気になる等の性質を持つ。それは空諦であり、報身といえる。実相をありのままに把握することが正しい認識である。実相をそのままわが心に受け止め、それに対しどう価値創造していくか、どう対処するか、それが智慧である。
人をどう評価していくかという場合も、まず、その人に対する正しい認識なくして、どうして正しい判断が下しえようか。その人の表面の姿・行動のみを見、その人の本質を見失えば、判断を誤る。また、その人の本質はこういうものだときめつけて、時々刻々と移り変わる姿・行動をありのままに把握しないとすれば、やはり正しい認識とはいえない。その人の、姿・行動も、その人の特質・個性も、その人の本質も、全部、そのまま受け止めることが大事となる。
信心を根本にして、一切を見通していけるのである。
◇◇◇◇◇
池田会長は、H2Оが水蒸気となったり、あるいは氷となったり、あるいは冷水となったりするその姿・形が応身であり、H2Оの持つ特性が報身であり、H2Оそれ自体が法身だと説明されていますが、応身・報身・法身の三身の解釈がでたらめです。
相・性・体が元となって本末究竟する十如是の説明を用いておりますが、相は仮・性は空・体は中なのですが仮が姿・形とするまでは良いのですが空諦・中諦の説明がまるでなっていません。池田会長は「本質」や「実体」という言葉を良く使いますが、実体や本質を説くのは仏法ではなく外道です。我や本質が「有る」と見るのが外道で、我も本質も「無い」と見るいわゆる「無我・無自性」を説くのが仏法です。「我有り・本質有り」は「有(実体)」に執着した物の見方で釈迦在世のインドではこの外道義が強くはびこっていました。釈迦在世の直弟子達のことを「声聞の弟子」と呼びますが、「有」に対する執着が強い仏法修行者の境涯のことを「声聞」といいます。
「声聞」に対して「観音」という仏法用語があります。「声聞」は声を「聞く」ですが「観音」は音を「観じる」のです。音は通常聞くものですが、音を聞くのではなく音を観じると書いて「観音」。同じような意味合いで「見る」と「観る」の違いがあります。「見る」は私たちが目に映る様を認識する行為で「観る」は目を閉じて心で観んじる行為を意味します。目に映りこむ姿だけをとって真実とするのではなく、目には見えない部分をも感じ取ってはじめて物事の真実が見えてくる。といったことを池田会長は言わんとされているのでしょうが、それは仏法の初歩である蔵教であらわされた仮の真実、仮諦のお話です。
蔵教は声聞に対して説かれた説法で、声聞は「有」に執着した「声を聞く」境涯です。物は「見る」もので温度は「感じる」もの。食は「味わう」もので香りは「臭う」もの。いわゆる五感を頼りに生きている人達で「有」という実在(実体)に対する執着から抜けきれずにいる境涯です。
人は外界の物事を五感を駆使して認識します。そのことを仏法では五蘊とか五陰という言葉であらわしています。この五蘊で外界を認識することで立ち上がっている世界を五陰世間といいます。人は自身の五蘊(五陰ともいう)の働きによって自身を中心(視点)とした世界が立ち上がって現実の世界を認識していきます。また、人はそれぞれに異なった感性を持ち合わせていますので五蘊の働きも人それぞれで、それぞれに異なった世界がたちあがっています。健常者が認識する世界と眼が不自由な人が認識する世界とでは全く違った世界が立ち上がっていることを考えれば解り易いかと思います。
このように感性の違い(五蘊の働きの違い)から同じ空間であっても人はそれぞれ異なる自分だけの世界を立ち上げて、それを世界として認識しています。その事を境涯(生命の状態)もふまえて説き顕されたのが一念三千の法門の中の三世間の一つ、五陰世間になります。
五陰世間は間性の違い、境涯の違いといった個々人の性質の違いが大きく関わると同時に、心の状態にも大きく関わってきます。その心の働きを詳しく説き顕した法門が十如是です。先に紹介しました御書の「千如は総て空の義なれば空諦の一なり」に当てはまる部分です。
色・受・想・行・識(五蘊)
お釈迦様は一仏乗の法華経があまりにも複雑で高度な教えな為、解り易いように三つにひも解いて説き明かしていきます。いわゆる三乗の教えです。蔵教で仮諦を説き、通教で空諦を、別教で中諦が説かれます。法華経は一念三千の法門を説きあかした経文ですが、その一念三千の法門を像法時代に天台が初めて理論的に説き明かします(理の一念三千)。一念三千の法門は法華経以前において明かされてきた三乗の教え、即ち仮諦・空諦・中諦の三諦がすべからく法華経に集約することが「開三顕一」として法華経迹門の三周の説法として明確に示されています。
蔵教・通教・別教において個別に説かれてきた空・仮・中の三諦が法華経迹門において円融することがあかされ、それを解り易くひも解いて解説したのが天台の理の一念三千です。
天台が一念三千の法門を解説する際に用いる華厳経に説かれる「心は工(たくみ)なる画師の如く種種の五陰を造る」の文は、大聖人様も『一念三千理事』や『三世諸仏総勘文教相廃立』等の御書の中で引用されています。自身の心が造りだす世界が五陰世間で、その世界は自身の心の状態が変わればまた違った別の世界にも見えてきます。自身の心の状態(境涯)次第でどのようにも変化する世界が五陰世間であり「空」の意味するところです。
五陰とは、「色・受・想・行・識」のことで人間が外の世界を認識する働きを示したもので、色(しき)は、色相を意味し受(じゅ)はそれを感じ取る感覚いわゆる五感を意味します。人は外界のありさま(色相)を自身の肉体に具わる感覚器官である五感をもって感じ取り、感じ取った情報を脳の中の記憶と照らし合わせて行動に転じます。この記憶と照らし合わせる作業を想像の「想」をもってあわらし、行動に転じてその一連の結果が認識として統合され記憶に蓄えられていきます。
職場で苦手な上司がいるとします。なぜ苦手なのかと言えば、過去にその上司との間で嫌な経験があったからです。ですからその上司の顔(色相)を見る(受)と過去の嫌な記憶がよみがえって(想)、避けるように身を隠します(行)。その一連の行動が自身の記憶の中に識として蓄えられていきます。認識出来る意識層が第六識の表層意識ですが、本人の意識が及ばない深層意識にトラウマとなって潜在的に深く刻まれる記憶もあります。
六識や表層意識、深層意識という言葉は天親菩薩が大成した唯識思想の中で用いられる言葉ですが、天親は御書『波木井三郎殿御返事』の中で「正法一千年には竜樹・天親等・仏の御使と為って法を弘む」(P.1372)とあるように竜樹と並ぶ正法時代の仏法の正統な継承者で仏の滅後に衆生のよりどころとなった四依の大菩薩の一人です。複雑な一念三千の法門を竜樹が「空」を専門に、天親が「唯識」を専門に扱いひも解いていきます。
「心は工(たくみ)なる画師の如く種種の五陰を造る」の経文に示されるように「色・受・想・行・識」といった自身の五陰の働きによって我々は自身を取り巻く世界を立ち上げています。そしてその立ち上がった世界に存在する姿、仏法では色相と言いますがその姿もまた、自身の心次第でいかようにも変化します。我々が認識している世界は自身の心が勝手に造りだしている幻影のようなもので、変化することなくそのまま存在し続けるものは一つとして無いのです。
ですから「無我」であり「無自性」であって一時的に仮に認識している姿に過ぎません。
その一時的に仮に佇む姿、「仮」について更に詳しく掘り下げてお話してまいります。
仮諦
まず、「仮」といいましても「仮観」と「仮諦」があるのですが、先に紹介しました池田氏の三諦論のようにこの二つを混同してしまっている仏法者が沢山います。「仮諦」がなんたるか、また一念三千が何たるかが正しく理解出来ていないとこのような誤った解釈をしてしまいます。
「仮」は、仮に佇む姿を指して「仮」といいます。では「仮観」はと言いますと、これは天台宗で説かれる修行法「一心三観」の仮観のことを指します。一心三観は一心に三を観じる観法で、ここでいう三は仮観・空観・中観をいいます。
人が物事を認識するさい、客観認識と主観とに別けられます。客観認識は誰が見ても、誰が行ってものように万人に共通する立場で物事を捉えることをいいます。それに対して主観は万人とは無関係に自身が個人的に感じとる自分一個の意見をいいます。
化学や医学は客観認識がベースとなって成り立っています。誰がリンゴを落としても地面に落下するから「引力の法則」が成り立つ訳で、人はみな声帯を使ってしゃべるから医学が成り立ちます。1と1を足したら二つになるから数学が成り立ちます。すべて客観性に基づいて展開されたのが医学であり化学であり数学です。
では文学はといいますと主観の世界のように思うかもしれませんが、文を読んで感じ取るその感じ方は主観ですが読み取る文は客観によって表現されたものです。
国語辞典に「楽しい」という言葉はこういう事をいうのだと定義づけがなされているから共通認識言として成り立っているのです。また主観で感じた事を言葉に転換しなければ人には伝えられません。言葉という共通認識言に転換した時点ですでに主観は客観に変わっています。
あなたが食べたリンゴの「美味しい」と、私が食べたリンゴの「美味しい」とでは同じリンゴの「美味しい」であっても個々人の感性の違い(五陰の違い)が生じますので全く同じ「美味しい」ではありません。個々人が感じ取る主観は定義ずけられた言葉に転じた時点で既に客観に変わっています。
このように我々人間が生活の中で用いる言葉も含めて文学や数学、医学や科学や哲学といったものは全て客観をベースに発展されてきたものです。
仏法はそのような客観による認識から離れて主観で物事を捉える修行を行います。どうして客観から離れるのかというと、客観認識の中にこそ人々を苦しめる苦の原因が潜んでいるからです。そこのところはまた別の機会に詳しくお話するとしまして、要は人の人生は客観ではなく主観そのものであるという点でお話を続けさせて頂きます。
一人の人間が「おぎゃー!」と生まれて、年老いて死んでいくまでに、何をどのように感じながら生きていくかという、まさに主観の中の出来事がその人の人生です。
仏法はその主観を軸として成り立っています。客観性をベースにした医学や化学、哲学などとは全く立ち位置が異なります。海の生き物と陸の生き物とでは、呼吸の仕方も進み方も全く異なるように、主観を説いた仏法と客観を説いた医学や化学や哲学とでは、捉え方が全く違うということです。
それを仏法を医学や化学や哲学と同じ次元で語っているのが創価学会です。水がお湯になったり氷になったり、はたまた水蒸気となって姿が見えなくなったりとかいう池田会長の三諦論は化学のお話です。化学の話しをあたかも仏法であるかのように話しているのです。
仏法はモノのありかたを説いた教えではありません。モノの方ではなく、モノをモノと認識する人の心を説いているのが仏法です。モノの有無のような心の外の事を説く教えを仏法では外道と言います。
お釈迦様は「モノの有る無し」といった二辺から離れた中道(縁起)を説きます。
「モノの有る無し」で説く科学や医学、哲学も文学も政治学もあらゆる学問・学術すべてが客観性をベースとして展開されています。そういった「モノの有る無し」から離れて仏法では〝縁起〟を真理として説きます。縁起を真理とする仏法を〝真諦〟と言いい、それに対して世間一般における真理を〝俗諦〟と言います。
池田氏の三諦論のように〝真諦〟と〝俗諦〟を同じ次元でごちゃ混ぜにして語ることは、高い教えと低い教えをごちゃ混ぜにしてしまい仏法を汚す行為として大聖人様は推尊入卑の謗法として開目抄の中で厳しく戒められています。(開目抄上 P.189)
我々は外の世界の情報を主観で感じ取り、それを客観認識の言葉に転換して意思の疎通を行います。主観で感じ取るさいに眼や耳や鼻や口や肌といった五感を駆使して様々な情報を察知して実体を捉え、客観的な認識として医学や科学、哲学といった学識として自身の意識層に蓄えられていきます。
この「色・受・想・行・識」といった第1~第6意識までの表層意識の働きによって形成される世界を衆生世間と言います。
我々衆生は、自身の五蘊の働きによって実在の世界を主観と客観とで認識している訳ですが、仏法では更に仮観という認識を用います。それが縁起です。
縁起によって仮に佇む姿が実在であって、縁が変わればその姿もまた変わって顕れます。ですから実在ではなく仮在と見るのが「仮観」です。
「仮観」は凡夫の所作(認識法)です。それに対し「仮諦」は仏の悟りです。「仮諦」の「諦」という字は「あきらかにする」とか「真実」といった意味を含んだ言葉で、「仮諦」とは仏の悟りを意味します。仮観と仮諦は混同してしまいがちなので、この違いについてもう少し詳しくお話しさせて頂きます。
仮観という観法は、五感の働きを沈めて自身の意識を表層意識から深層意識へと移行させます。表層意識とは九識論で言うところの六識までの我々が意識として認識出来る識層のことで、五陰世間のところでお話しました「色・受・想・行・識」、いわゆる五蘊が働く場所です。
眼・耳・鼻・口・肌の五識で外界の情報を感じとって六識で「意識」として統合されて我々が日常認識している実在の世界が立ち上がります。
立ち上がった世界は実は実在すると思い込んでいるだけで、実際は人それぞれに見え方あり方は異なっており、また自身の心の状態の変化によっても認識するその姿は変わってきます。世の中には常に変わらず存在し続ける物は何一つ存在しえません。ですから「無我」であり「無自性」なのです。ただ「縁」によってさまざまな姿をあらわす「縁起の法門」があるだけで、それが仏が悟られた「仮」の真実、「仮諦」です。仮諦が詳しく説かれたのは時代で言えば正法時代、教えで言えば蔵教です。
蔵教
蔵教は天台が釈迦一代の説法をその教えの内容から振り分けた蔵教・通教・別教・円教の四教の中の仏法の初歩の教えにあたります。
四教はそれぞれの境涯に即した形でそれぞれの法が説かれており、蔵教は声聞の為に、通教は縁覚の為に、別教は菩薩の為に、そして円教は末法の衆生の為に法が説かれています。
蔵教が説かれた釈迦在世の正法時代は、外道思想が強くはびこっていた時代でもあります。外道とは書いて字の如く、外にあらわれた認識出来る範囲でしか物事を捉えようとしない実体思想のことですが、創価学会や日蓮正宗では三世を説いていないキリスト教のことを、「内道」の仏法に対して「外道」と定義づけしています。
「外道」とはキリスト教のような今世しか説いていない教えのみを指していう言葉ではありません。仏法の中にも外道は存在します。大聖人様は「外道」について『一代聖教大意』(P.403)の中で
「外道に三人あり、一には仏法外の外道 九十五種の外道、 二には学仏法成の外道 小乗、 三には附仏法の外道 妙法を知らざる大乗の外道なり」
と外道に三種あることを示されています。一の仏法外の外道は創価学会や日蓮正宗でいうところの内道を説かない外道で分かり易いのですが、二の「学仏法成の外道」と三の「附仏法の外道」が解り難いので『十法界事』(P.418)の中で大聖人様は詳しく述べられています。
御抄を拝読すれば、「学仏法成の外道」とは仏法を学んで尚外道から抜けきらない小乗教の析空に陥った仏法修行者のことであることが十分にご理解頂けるかと思います。
釈迦は外道の教えを破る為に「無我」を説いたのですが、小乗の声聞の弟子達は「無我」の教えに執着するあまり、かえって迷いを生じて、煩悩が出てくる源である身体と心とをともに滅するという色心俱滅の見解に陥ります。いわゆる灰身滅智(けしんめっち)です。
身も心も無に帰して消滅してしまうという灰身滅智は、無我を誤って解釈した「析空」にあたります。析空に対して空を正しく理解した竜樹が通教において展開した空理(空の理論)を「体空」といいます。
無我を悟りながらも未だ実体思想から抜けきらないでいる仏法者を「小乗の外道」と言うのだと大聖人様は『一代聖教大意』の中で御指南あそばされていますが、仏法の因果や縁起の法門を医学や化学、哲学といった客観認識(実体思想)で語っている創価学会の仏法がまさにそれにあたります。
「析空」と「体空」の違いは、蔵教と通教の違いでもあり境涯でいえば声聞と縁覚の悟りの深さの違いでもあります。声聞という境涯は未だ実体思想から完全に抜けきれづにいる仏法修行者なので空を客観認識(実体思想)で理解してしまうのです。
「析空」はウィキペディアを見ると、「ものの在り方を分析して、実体と呼べるもの、いつまでも変らずに存在するものが、ものの中に無いことを観ていくこと」とあります。
つまり机を例にとってみると、その脚を外してしまえば単なる板と棒になってしまい何も減じていないのに、机そのものの存在は無くなります。池田会長の水と水蒸気の関係と同じ理論です。
机は仮の姿であって「仮」であるがばらしてしまえば板と棒であって机の姿は無くなって「空」となる。このような空の解釈を「析空」と言います。
説一切有部に代表されるこの析空は、主観にあたる我は空だが、認識として働く法(五蘊)は三世に渡って実在するとみます。
その説一切有部の空理を般若心経で説かれる「色即是空」をひも解いて、法(五蘊)も空じる対象であることを示したのが竜樹です。
先の机の話でいえば、机をばらして天板と脚にすると確かに机の姿はなくなります。しかし「体空」の見方は五蘊を空じるわけですから「見る」のではなく眼をとじて「観る」という観法に入るのです。
五蘊を空じて表層意識による認識を止めて、深層意識で観じ取っていきます。何を観じとっていくかは、人それぞれでしょう。ある人にはその机を一生懸命製作している職人の姿が観えてきたり、またある人にはその机を使って一生懸命勉学に打ち込む学生の姿が観えてきたり。
「析空」が存在を縁起のかたまりと捉えて種々の構成要素に分析して「空」を悟るのに対して、「体空」は、「見る」認識から「観る」観法へと自身の物事の捉え方を変えることで悟る「空」なのです。
析空=モノの有り様を捉えた空
体空=人の認識の有り様を捉えた空
「体空」を得ることで実体から抜け出て仏の世界観である空観に入ることで境涯が声聞から縁覚へと昇進します。境涯が変わることで認識する世界観も変わって来ます。
声聞=衆生世間(実在)主観と客観
縁覚=五陰世間(非実在)空観
未だ実体思想から抜けきらないでいる声聞の弟子達に、実体に即して説かれた教えが蔵教でそこで示された真理が「仮諦」です。「声聞の弟子」といわれる所以は「物を見る」ように声を聞く境涯だからです。
「体空」を悟って正しい「空理」に立って初めて仮から空へ進めます。空は般若心経の中で観音菩薩によって説かれますが、音を観じると書いて「観音」。声を聞く「声聞」よりも更に一段高い境涯の教えです。
唯識
人の意識には表層意識と深層意識とがあります。表層意識は我々が日常において五感を使って意識として認識している意識で、深層意識は意識の及ばないところで働いている意識です。
認識できる識層が意識なので深層意識は正確には末那識や阿頼耶識といった「識」にあたります。これは「唯識」といって、前五識(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)と意識と二層の無意識の八種類の「識」とによって成り立つ大乗仏教の見解の一つで、創価学会や日蓮正宗では「九識論」として教えられている教学です。
深層意識は七識のマナ識(末那識)、八識のアラヤ識(阿頼耶識)、更に奥底に九識のアマラ識(阿摩羅識)とがあります。アマラ識のことを「仏識」ともいって、大聖人様は「九識心王真如の都」とも「南無妙法蓮華経」とも呼ばれています。
表層意識である前五識の視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚が五蘊の働きとなって物事を実体視し、実体思想を生み出します。その五蘊の働きを空じることで辿りつく識層が深層意識と呼ばれる識層です。
マナ識 (末那識)
自我執着心が眠る七識のマナ識は、人間が本能的に自身を守る為に無意識のうちに働く識層です。心臓や内臓などが私達の意識とは関係なく活動し続けていることや、お腹が空いたり眠くなったりといった食欲、睡眠欲や物に執着する物欲、金銭欲など、人間には本能的に生きて行く為に備わっているさまざまな欲があります。
このような意識とは全く無関係に、「無意識的」に活動を続けているところがマナ識です。私達が自分のことを「自分」と認識するいわゆる自我と呼ばれるものが生まれるのもこのマナ識の働きです。
眼の前に二つの手があるとします。片方はあなたの手。もう片方は他人の手。この二つの手の違いはなんでしょう?
自分の手は自分の想い通りに動かすことが出来ます。他人の手の方は自分の想い通りには動かせません。人は自分の想い通りにならない時にストレスを感じたり苦しみが生じたりします。
仕事が思い通りにならなかったり、恋愛が想い通りにならなかったり、子育てが思うようにならなかったり、お金が思い通りにならなかったりで人生なかなか自分の想い通りにはならないものです。そのような時、人は悩み苦しんだりします。悩みや苦しみの根源には必ずこの「自分」という自己意識の存在があってこれを「自我」といいます。
仏法では人間の苦しみの根源を煩悩といいますが、実はこの煩悩は全て「自我」から生じています。自我がもととなって我癡・我見・我慢・我愛の四煩悩が生じます。
我癡(がち)は自己に対する愚かさで別名を無明とも言います。人生や事物の真相に明らかでなく、すべては無常であり固定的なものは何もない(無我)という事実に無知なことです。
この無明=我癡が根本原因となって,あとの我見・我慢・我愛の3煩悩が生じてきます。我見(がけん)は自分という我に執着する心で他者と自分を立て別けて見ることをいいます。
物事の真実に明らかでない我々凡夫は、本来は「而二不二」である自分と他人とを別視して分別してしまいます。他者と自分を分別する心から、今度は他者よりも自分は優れている勝っているという自身への慢心、我慢が生じます。
我慢(がまん)は次の七慢(①慢、②過慢、③慢過慢、④我慢、⑤増上慢、⑥卑慢、⑦邪慢)からなります。
①慢とは、無意識下にある我という観念により、相手に対抗してしまうこと。
②過慢とは、自分と対等または優れたものに対し、潜在的に自分のほうが良い、自分も同等にできると思うこと。
③慢過慢とは、自分より優れたものに対して、自分のほうが良い、と段々高慢が高じてくること。
④我慢とは、自分にこだわり、自分のほうが相手より優れていると思い上がる気持ちのこと。
⑤増上慢とは、自分ではわかっていない境地を、証得したかのようにふるまうこと。
⑥卑慢とは、自分よりはるかに優れた人に対し、「たいしたことは無い」と思う慢心。
⑦邪慢とは、自分にまったく徳が無いのに徳があると思い込むこと。
このような我慢が働いて最終的に自己に対する愛着、「我愛(があい)」が深まっていきます。
職場には嫌な先輩や苦手な上司が必ず一人は居るものです。しかしそういった人物の存在を見方を変えることで自身の欠点や克服すべき課題に気づかせてくれている有難い存在であると捉えて感謝の心で接していけるようになっていくのが仏法の素晴らしいところです。
自我に執着すると人は自分と他人を隔てて見てしまいます。しかし自我への執着から離れることで他者は自分の一部であるという「而二不二(二にして二に非ず)」の境地に入っていきます。そして人としてあるべき正しい姿を顕していきます。
仏法は法則を説いたものではありません。法則は誰がりんごを落としても地面に落下するように、誰が見ても太陽は東から昇って西に沈むように万人に共通する客観性を解いたものです。
仏法の中で説かれているのはそのような「法則」ではなく、「法門」が説かれているのです。「法門」は仏の智慧であり悟りです。そしてそれは仏しか知りえません。お釈迦様は自身が習得した仏の境地を智慧第一といわれた弟子、舎利弗に伝えようとしますが、
「止めておこう、舎利弗よ、もうこれ以上話すのを止めよう。なぜなら、仏の習得したものは、最高に稀有で難しい法なのだ。ただ仏どうしがよく仏法の真実を見極めることができる」
と伝えることを止めます。言葉で伝えるということは、お釈迦様が悟りえた主観を「言葉」という客観に転換しなければなりません。
しかし客観に展開してしまえば、お釈迦様が主観で悟りえた仏の境地ではなくなります。仏の悟りは客観では伝えることは出来ないのです。
医学や化学や哲学をもってしても、説明しきれないのが仏様の悟りえた真実です。その真実を可能な限り主観に基づいて言葉で顕されたのがお釈迦様の一代聖教です。
限界ぎりぎりの所まで言葉を用いて主観の仏法を説き顕し、そこから先は言葉を離れるといった手法で仏法は説かれています。
法華経の迹門と本門がまさにその「言葉を離れる」境界にあたります。理論をもって説かれる一念三千と心で観じ取っていく一念三千の違いです。
何を観じ取っていくのかといった具体的なお話は、話し出すと長くなりますので次章で詳しくお話したいと思います。
お釈迦様は自身が悟りえた主観を、未だ実体思想から抜け切らないでいる声聞の境涯の弟子達にも理解出来るように、実体に即した客観の言葉を用いて説いていきます。
それが仏法の初歩の教えである蔵教で説かれた「仮諦」です。この声聞の弟子達は師匠であるお釈迦様の声(説法)を聞いて悟る境涯なので「声聞」なのです。
空の世界観
蔵教の中で説かれる「仮」の真実は、縁起によって仮に佇む世界を我々は認識しているといった「縁起の法門」です。
その縁起の法門を正しく理解できた(体空を悟った)竜樹や天親が次のステップである通教の中で「空」と「唯識」をそれぞれに展開し空諦(五陰世間)をひも解いていきます。
竜樹や天親は、実体に捕らわれた「声聞」とは違い、縁にふれながら覚りを開いていく「縁覚」という境涯で、そこには師匠の姿(実体)は無いので独覚ともいいます。
空を悟った境涯に師匠の実体は必要ありません。実体は有りませんが師匠は現として存在し法を説き続けます。そのことが私達が毎日唱える「自我偈」の中に次のように示されています。
「人々を救うために、一度は(釈迦として)死んだ姿をとりましたが、実際に死んだのではなく、常にこの世界にいて法を説いているのです。私は常にこの世に現れていますが、神通力によって迷っている人々には、姿を見せないようにしているのです。人々は私の死を見て、私の遺骨を供養し、私をなつかしく思い、慕い敬う心を起こしました。人々が信仰心を起こし、心が素直になり、仏に会いたいと願い、そのために命も惜しまないように、その時私は、弟子たちと霊鷲山に姿を現します。そして人々に語ります。
「私は常にこの世界にあって不滅ですが、人々を導く手段として死んでみせたのです」と。他の国土の人々も、私を信じ敬うならば、その人々のためにも、私は最高の教えを説くでしょう」
視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の前五識によって「意識」として認識するのが肉体と脳の働きです。「空」を悟った通教の縁覚は、禅定によってそれらの働きを空じて意識をより深いマナ識・アラヤ識へと向かわせます。
そして見えない(実在しない)お釈迦様を観じ取っていきます。どうして観じ取っていけるのかというと、アラヤ識には過去遠遠劫よりのお釈迦様の記憶が蓄えられているからです。
また記憶だけでなく現行のお釈迦様の意識も更に奥低に仏性として現在しています。この肉体から生じる実体への執着から離れた境涯が空を悟った縁覚の境涯です。
空を知らない創価学会や日蓮正宗の人達は、一念三千の法門を十界論を中心に説明します。前世の行いが縁となって今世の十界の差別の色相(実体)として現れるという彼らの説明は実体に即した「仮諦の一念三千」です。
創価学会や日蓮正宗の人達が言う一念三千も確かに一念三千の法門です。しかし実体思想から離れて心を空じることで現れてくる別次元の一念三千があります。
自身の心(境涯)が変われば同じ人物も同じ空間も感じ方、見え方が変わって十界の変化が生じてくるといった心(十如是)を中心に現れてくる「空諦の一念三千」です。(五陰世間)
更に三身に即して現れる一念三千が「中諦の一念三千」なのですがその説明は後ほどするとしまして、要は一念三千といいましても仮諦・空諦・中諦の一念三千が仮諦→空諦→中諦と円融していくことを「三諦の円融」というのです。
水が氷になったり水蒸気になったりする化学のお話でも、若々しい青年期と枯れ果てた老年期における肉体の変化のお話でもありません。
勤行の時に十如是を3回くり返して読み唱えるのも、この三諦の円融を意味しています。自身の意識を仮(表層意識)から空(深層意識)へ、さらに九識の仏性へと向かわせる為の三転読誦なのです。
アラヤ識(阿頼耶識)
人々の記憶が一堂に蓄えられているのが八識のアラヤ識です。アラヤ識の特徴はここでの意識は共有されるというものです。七識の自我が自他を分別して六識から前五識を形成しています。その下位に位置する八識のアラヤ識には自我や自他といった意識は存在しません。肉体も自我も存在していないので蓄えられた記憶は個々人の「意識」ではなくただ「識」としてアラヤ識に蓄えられていきます。
自我意識が存在しないこのアラヤ識では自他の分別は生じません。自他の区別を無くした境涯を菩薩と言いますが、このアラヤ識における意識の共有がそれにあたります。
実体(思想)を認識する五感(前五識)と、実体思想を立ち上げている第六識の「意識」、この六つの表層意識に心が覆われているのが凡夫の境涯です。
仏門に入って瞑想で深層に意識を向かわせ、煩悩が生じる自我を中心としたマナ識と向かい合う境涯が声聞・縁覚になります。そして自我意識よりも更に深く自他の区別が無くなった意識それが菩薩の境涯であるアラヤ識となります。
仏法では慈悲という言葉をよく使いますが、慈悲とはすべての命に共感していける菩薩の心のことで、世の中の全ての人々に対して、苦を抜いて楽を与えたいと言う「抜苦与楽(ばっくよらく)」の菩薩の心を現わしたものです。
分別と無分別
仏法では苦しみのもととなっている煩悩の根源にある「自我」と向き合い、いかにしてそれを退治していくかが詳しく説かれています。
人と言い争っている場面を想像してみて下さい。互いの主張がぶつかり合って互いが互いの「自分」をぶつけ合います。互いに「自分が正しい」と思い込んでいる心がそうさせているのです。
「俺が正しい」「私が正しい」と自分の「我」を強く主張すればする程言い合いは益々エスカレートしていきます。しかし、その「我」を「私が悪かった」とひっこめれば、喧嘩にはなりません。
世の中の対立や紛争、身近なところでは夫婦の不仲、親子関係のこじれなどこれらは全て「自我」によってもたらされた不幸です。
人は自分が理解出来ないことをする人に対してイラダチや腹立たしさを感じます。それが発展して様々な対立が起きてきます。不理解がもたらす対立です。
私達は、ついつい自身の価値観で物事を判断し、相手には相手の価値観があるということを忘れてしまいがちです。
忘れていなくても相手の言っている事は「間違っている」「自分の方が正しい」のだと思い込んだりしてしまうこともあります。自分にとっては確かにそれが正解であったとしても、育った環境や価値観が全く異なる人にとってはまた別の正解があったりもします。
なのに人はついつい自分色のサングラスをかけて物事を見てしまい自分の価値観で物事を判断してしまいます。
それは「自我」が奥底に潜んでいるからです。その自我がどうして起こるのかというと、自他を分別する心があるからです。
その分別の心に対して仏法では無分別を説きます。「無分別」は、創価学会や日蓮正宗の人達には聞きなれない言葉だと思いますが大聖人様は『三世諸仏総勘文教相廃立』P.561の中で、
「方便品に云く「三世の諸仏の説法の儀式の如く我も今亦是くの如く無分別の法を説く」已上、無分別の法とは一乗の妙法なり」
と仰せの通り、妙法とは無分別の法であるとのべられています。
先にお話しました医学や化学、哲学といった客観性をベースとして展開されてきた部類は全て分別から生じたものです。臓器の働きの違い、分子の違い、化学反応の違い、思想の違い、言葉の違い、表現の違い、といった具合です。
そのような客観性や分別そして自我から離れたところに「空」があり「無我・無自性」があります。
自我への執着から煩悩が生じるとして蔵教では「無我・無自性」が説かれます。蔵教の中で示された四諦や八正道は自我意識を退治する為の教えで、実体思想にとらわれている声聞の弟子達に分かりやすいように実体に即した内容で示されています。
<四諦>
苦諦(くたい)
迷いのこの世は一切が苦であるという真実。
集諦(じったい)
苦の原因は煩悩・妄執、求めて飽かない愛執であるという真実。
滅諦(めったい)
執着を断つことが、苦しみを滅した悟りの境地であるということ。
道諦(どうたい)
悟りに至るためには八正道によるべきであるということ。
<八正道>
1.正見(しょうけん)
正しく見ると書くように、ありのままに見ること。
2.正思惟(しょうしゆい)
正しく考えること、正しい意志を持つこと。欲や怒り、ねたみやうらみを離れること。
3.正語(しょうご)
正しい言葉を使うこと。お世辞や二枚舌、悪口やウソを離れること。
4.正業(しょうごう)
正しい行為をすること。生き物をむやみに殺したり(殺生)、他人のものを盗んだり、よこしまな男女関係(邪淫)を造ったりしないこと。
5.正命(しょうみょう)
正しい生活をすること。戒律を守り、正しい生き方をするということ。
6.正精進(しょうしょうじん)
正しいところへ向って努力すること。仏法に説かれる真実を探求する努力を怠らないこと。
7.正念(しょうねん)
正しい信念を持つこと。仏法に説かれる真理を信念として生きること。
8.正定(しょうじょう)
心をしずめて一つに集中することで、1から7を総括したもの。
八正道の内容はどれも現実社会における身の置き方、心の有り様で実体思想にもとづいた修行法として示されています。
通教
大聖人様は『三世諸仏総勘文教相廃立』の中で、
「蔵通別円は即ち声聞・縁覚・菩薩・仏乗なり」
と仰せになられ、蔵・通・別・円の四教が声聞・縁覚・菩薩・仏の境涯に即した教えであると御指南あそばされています。
「縁起」で析空を悟った声聞から更に体空を悟って「色即是空」を観じとっていく縁覚、「自我」を空じた縁覚が「而二不二」の菩薩の境地へと入っていきます。
この境涯の変化は第六意識からマナ識、アラヤ識、そして九識心王真如の都と大聖人様が仰せになられた南無妙法蓮華経へと意識が変わっていく意識の変化でもあります。
実体に即して説かれた仮の真実、「仮諦」が声聞に対して説かれた教えなのに対し、縁覚には通教の中で「十二因縁」が示されます。
十二因縁は、人間が母親の胎内から生まれ、生をまっとうして死に至るまでの間を「無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死」の十二の行程に分け、一切の現象は私たちの心に原因があり、現在、生かされている業(行為)が深層意識にすり込まれ、前世などの過去世を含めた時代の業にも影響しあって、現在のそれぞれの幸・不幸が決まることが説かれています。
<十二因縁>
1.「無明(むみょう)」とは煩悩のことです。人間が過去世で起こした一切の煩悩のこと。
2.「行(ぎょう)」とは行為のことで前生で行った業です。人間が過去世で煩悩によってつくってきた様々な業(善悪の行為)のこと。
3.「識(しき)」とは過去世の煩悩と業によって、この世の母親の胎内で生を受ける最初の心。最初の一念。
4.「名色(みょうしき)」とは、識が具体的な形となったものです。「名色」の「名」は心、「色」は形を表しています。受胎して眼や耳ができるまでの約4週間程度です。
5.「六処(ろくしょ)」とは、眼、耳、鼻、舌、身、意の六感ができて出産するまでの三十四週間の間。六根が発達して胎内で盛んに動きだすようになる姿。
6.「触(そく)」とは、生まれてから二、三歳までの間。初めて外界の物に触れ、苦楽を感じる事なく事物を感覚し始める時期。
7.「受(じゅ)」とは、外界から種々の言語や知識を受け取る時代。四、五歳から十四、十五才までの期間。苦楽を識別しながら外から様々なことを受け入れながら人格が形成されていく。
8.「愛(あい)」とは、精神が発達して次第に色欲も強くなっていく十五、十六歳からの青年期。物質的欲求が激しくなり、異性に対する愛情も強くあらわれる。
9.「取(しゅ)」は、欲望がますます激しく起きる二十五、二十六歳から五十歳位までの時代。色欲、物欲、名誉欲すべて旺盛で生涯の中で煩悩が一番強い。あれが欲しい、これが欲しい、ほめられたい、認められたいという欲の心が盛んな時代。
10.「有(う)」とは、生存によって欲望やそれに執着することから未来に再び生まれ出る結果が定まること。ここまで積み重ねてきた業によって未来の果報を有すること。「愛」「取」の煩悩に引きずられ、色々な悪業を造って未来に輪廻転生する種を残します。
11.「生(しょう)」とは、現世に造った業によって未来に生まれることをいう。
12.「老死(ろうし)」とは、生まれてから老衰してやがて死んで行き、また未来世に生まれ輪廻するということ。
このように、十二因縁は三世にわたっており、
1番目から2番目までは過去世、
3番目から10番目までは現在世、
11番目、12番目は未来世
を示しています。
この十二因縁は心から全てが生じる性の十如是を説いたものでその因縁は現在・過去・未来の三世におよぶことが示されています。
人の行いは本人の意思に関係なく全て無意識のうちにアラヤ識に蓄えられていきます。それら自身の前世の行為が因となって現在の自身の姿(果)が形成されています。『開目抄』で仰せの、
「過去の因を知らんと欲せば其の現在の果を見よ未来の果を知らんと欲せば其の現在の因を見よ」
の御文の通りです。声聞は前五識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識)からなる意識(第六識)を中心とした未だ実体思想にとらわれた境涯ですが縁覚はこれらの表層意識を空じることでマナ識・アラヤ識を観じとっていく境涯です。
表層意識を空じることを五蘊を空じると言います。これは般若心経の「照見五蘊皆空」の句によるところですが、人が物事を認識する作用である「色受想行識」の五蘊を空じることで、ものごとのありようは全て条件によって変わるもので、そのもの自体には本質や実態は無く「無我・無自性」であるという真理を得ます。
「色受想行識」という五蘊の認識作用は肉体から生じる作用です。仏法でよく解脱という言葉を耳にしますが肉体からの解脱とは五蘊を空じることを意味します。
肉体がある限り五蘊に惑わされ煩悩が生じます。ですからその肉体を完全に焼き尽くして涅槃に入ろうとして灰身滅智するのが析空で空に入る声聞です。身を灰にして智をも滅してしまいます。
それに対し体空で空に入る縁覚は、空の中にある「智」、すなわち仏の智慧を観じとって悟りを深めていきます。
声聞という境涯は仏の声を聞くことで仏門に入っていくのですが「声を聞く」というのは五蘊による認識作用です。それに対し縁覚は独覚ともいわれるとおり一人で悟りを得ていきます。縁覚は五蘊を空じることで空の中に仏の一大事因縁を観じて悟りを得ます。ですから「縁覚」というのです。
一大事因縁とは「仏はただ一つの大事をなす為だけにこの世に現れる」という「一大事の因縁」です。『御義口伝巻上』の中で(御書P.717)、
「一とは中諦・大とは空諦・事とは仮諦なり此の円融の三諦は何物ぞ所謂南無妙法蓮華経是なり」
と大聖人様が仰せの一大事です。空の中に一大事の因縁を観じとった縁覚は通教の中で空諦を顕していきます。それが竜樹が顕した「中論」です。
「中論」の中で竜樹は、お釈迦さまと同じ思想にたって「実体観」を破析し、十二縁起を用いて「無自性」を説き、
「縁起」→「無自性」→「空」
といった理論で、「縁起」という関係性の中であらゆるものは認識され、縁する対象が変われば認識もまた変わるとして「すべてのものは実体がなく空である」としています。
そして竜樹は「空」を実体の有と非実体の無のどちらにも属しない「中道」の「非有非無」として真俗の二諦説を説きます。
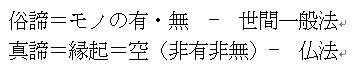
俗諦は「世間的真理」で実体思想(実体観)における真理で、真諦は「出世間的真理」で仏法における真理をいいます。
竜樹の二諦説は空・仮・中の仮(俗諦)と空(真諦)のみで中諦は天台が別教の中で顕します。
別教
竜樹は般若心経の中で説かれる「空」をもって体空観を顕しますが、天台は維摩経の中で説かれる不二の法門をもちいて「而二不二」の中諦を顕します。
<天台の空・仮・中>
仮‐有
空‐空(非有非無)
中‐亦有亦空
蔵教で縁起と因果を悟って声聞となった阿羅漢は、通教で空を悟って縁覚となり、別教で不二の法門を悟って菩薩の境涯に至ります。九識で言えば自我が眠るマナ意識よりも更に深い階層のアラヤ識に入ったことになります。この識層では自我が生じないので自他の分別がおきない無分別の境地(菩薩の境涯)となります。
人の「悩み」の多くは、他者とのかかわりから起こっています。心理学者であるアドラーは「悩みとはすべからく対人関係の悩みである」と言っていますが、私達は社会の中で生きている以上、家族や友人、同僚や近所の人などさまざまな人達と関わりながら生きています。その関わりの中で、他者と比較されたり比較したりで、他者との軋轢(あつれき)による悩みが生じてきます。
仏法では、アラヤ識における無分別の境地に示されるように、自身と他者を区別して考えるのではなく一体と考えます。我々が現実として認識している世界は、分別の心から立ち上がっています。認識器官である前五識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識)は、すべて違いを見分ける器官です。他人と自分といった分別の心から自我が形成され、自我が生じることで我癡・我見・我慢・我愛の四煩悩が生じます。
ですからお釈迦様は「無我」を説いて自我への執着を遠ざけます。自我への執着が強い人は、「人からあなたは馬鹿ですね」と言われると感情のなすがまま激怒します。しかし自我への執着がない人は「この人には私はそういうふうに映っているんだ」と思うだけのことです。これが無我の境地です。
また人を見る時も、我見が強い人は自分の価値観で他者をも判断してしまいがちですが、我見が無い人は他者を無自性と見ます。状況によって変わる縁によって今は一時的にこのように顕れて見えているに過ぎない(仮観)と見るのです。常識や自身の価値観は世間一般的な真理で、それは実体にとらわれた実体観です。実体は実は無自性(仮観)で、我もまた無我である(空観)と観じることで中諦の真理が見えてきます。
自身が電車の中に居る場面を想像してみて下さい。
実体観で捉えると客観的に考えて立っている人は辛く座っている人は楽です。ですから座って楽にやり過ごしたいという欲が生じます。これが自身と他者を分別した我有りから生じる一般世間における心理です。我を打ち消して心が欲から離れると視界は外に広がり、困っている人に席を譲ってあげようという心理が働きます。自分が立っていればこの人は楽に居られると思えば、他者貢献の心で自身が満たされます。かりに自分が座っていたとしても立っている人がいるおかげで今自分は座って楽が出来ているんだと思えば「ありがとう」の感謝の心で満たされます。
このように自他を分別する心から離れて、自他を一体として捉える心が不二の法門です。二にして而も二に非ずの「而二不二」の悟りです。
表に現れた差別の色相(仮)は実在の「有」で、その「有」が認識世界を立ち上げています。その「有」を空じて心で観じとった先に「有」にも「空」にも偏らない中道としての而二不二の「中」があります。「有」でもあり「空」でもあり、また、「有」があるから「空」がある。この而二不二の「亦有亦空」が凡夫の真実の姿であり仮観、空観に対して「中観」といいます。
仮諦は実体に即した真実の姿、空諦は実体を空じることで現れてくる真実の姿、中諦はその両側面を分別することなく無分別で捉えていく中道としての而二不二で、有でもあり空でもある「亦有亦空」の凡夫の真実の姿です。「亦有亦空」が凡夫の真実の姿なのに対し、仏の真実の姿は「非有非空」です。仏の非有非空については次の章で詳しくお話しさせて頂くとして、蔵・通・別・円の四教は次の様に示すことが出来ます。
蔵教—声聞乗 有 仮諦
通教—縁覚乗 空 空諦
別教—菩薩乗 亦有亦空 中諦
円教—仏乗 非有非空 円融
乗は乗り物の喩えで教えを意味します。未だ実体思想から抜けきれずにいる声聞に対して説かれた蔵教の教え、そして体空を悟った縁覚に対して説かれた通教の教え、而二不二の中道の境地に至った菩薩に対して説かれた別教の教えとここまで順にお話してきました。
『三世諸仏総勘文教相廃立』の中で大聖人様は次のようにご教示あそばされています(P.560)。
「三蔵教より別教に至るまで四十二年の間の八教は皆ことごとく方便の教えであり、夢のなかの善悪を説いたものである。ただしばらくの間、衆生を誘引するために用いられた支度・方便の教えなのである。この権教のなかにも、それぞれに皆ことごとく方便と真実があり、権実の法が欠けていないのである。四教の一々にそれぞれ有門・空門・亦有亦空門・非有非空門の四門があって差別がないのである。また言葉も同じであり、文字にも違いがない。これによって、言葉に迷って権実の差別をわきまえないときを仏法が滅びるというのである」
この御文の前半部で蔵教・通教・別教が説かれた四十二年間の教えは方便の教えであると仰せです。ですから方便は用いず真実の教えである法華経だけを用いれば良いと思いこんでいるのが日蓮正宗及びその教学の流れをくむ創価学会です。
その後に「この権教のなかにも、それぞれに皆ことごとく方便と真実があり、権実の法が欠けていないのである。」と大聖人様は明確にお示しになり、更に「四教の一々にそれぞれ有門・空門・亦有亦空門・非有非空門の四門があって差別がないのである。」と仰せです。
権教(蔵・通・別)の中にも方便と真実とがあって蔵・通・別・円の四教の違いによって入り口は違えども、辿りつく到達点はみな同じであると言われております。解り易く言えば、有門の実体に即して説く一念三千(仮諦)も空に転じて説く空門の一念三千(空諦)も、中道(而二不二)を説く亦有亦空門の一念三千(中諦)も、全て中道一実の妙法に集約されると御指南あそばされているのです。
仮諦を説いた蔵教と、空諦を説いた通教と、中諦を説いた別教の三つの教えが円教である法華経によって円融する訳ですが法華経が説かれる以前の爾前経においては、蔵教を学び八正道を実践した声聞達は、通教の時代に縁覚に転生して十二因縁を悟り、別教の時代に菩薩として転生して六波羅蜜を実践して気の遠くなるような長い歴劫修行の果てにやっと仏の境地に辿りつきます。
中諦を中心に説かれた別教では華厳経の中で「毘盧遮那仏」が説かれ、大日経で「大日如来」がそれぞれ法身仏として説かれています。ここで説かれる仏は人の姿からかけ離れたいわゆる仏の三十二相を備えた色相荘厳仏です。十界互具が説かれていない時点においては凡夫は九界を離れて転生によって仏界に辿りつくしかありません。
また阿弥陀経の中で説かれる阿弥陀如来は仏界の仏が九界の衆生を他力によって涅槃へと導く「他力本願」の他受用身です。このような別教で説かれた九界から離れた仏のことを「厭離断九の仏(おんりだんくのほとけ)」といいます。
最初の方で外道のお話をしましたが、外道にも三種あって1番目が仏法外の外道いわゆるキリスト教などの三世を説かない教えで、2番目が仏法を学んでも未だ実体思想に捕らわれている小乗の外道(灰身滅智)、そして3番目の外道が大乗の外道でこの「厭離断九の仏」がそれにあたります。『十法界事』にそのことが詳しく示されています(418ページ 8行目~11行目)。
「大乗の菩薩に於て心生の十界を談ずと雖も而も心具の十界を論ぜず、又或る時は九界の色心を断尽して仏界の一理に進む是の故に自ら念わく三惑を断尽して変易の生を離れ寂光に生るべしと、然るに九界を滅すれば是れ則ち断見なり進んで仏界に昇れば即ち常見と為す九界の色心の常住を滅すと欲うは豈に九法界に迷惑するに非ずや」
(同ページ17行目に飛んで)
「故に釈に云く「円乗の外を名けて外道と為す」」
仏界の仏が九界の衆生を救い導くといった別教で説かれた仏(厭離断九の仏)のことを「他受用身」といいます。「他に受け与える」という意味です。何を受け与えるのかというと仏様が悟った境地であり仏の智慧です。別教で説かれる仏が「他受用身」なのに対して円教で説かれる仏は「自受用身」です。自受用身は「自らに受け用いる身」で、悟りによって得た法を自らに受け用いる仏のことです。法華経では十界互具が明かされることでこの「自受用身」が説かれています。
仏は必ず三通りの姿を備えていると経典に示されており、応身如来・報身如来・法身如来の三身如来がそれにあたります。他受用身や自受用身はこの中の報身如来のことで正確には他受用報身如来と自受用報身如来になります。
応身・報身・法身
応身・報身・法身の中の「法身」は「法」そのものを指して「法身」というのですが、ではどのような法かと言いますと、仏様が悟った様々な御法門のことで五十二の悟りがあると言われています。「縁起の法門」や「因果の法門」はその中の一つに過ぎません。
法華経以前の仏道修行者達は歴劫修行の中で蔵教・通教・別教の三乗の修行によってこの五十二の悟りを次第に悟っていきます。そして辿りつくのが厭離断九の他受用報身です。
実はこの別教の中で説かれる厭離断九の仏は、「毘盧遮那仏」も「大日如来」も共に架空の仏、「権仏」であると大聖人様は御教示あそばされています。どうして「権仏(仮に顕された仏)」かといいますと応身・報身・法身が一体でないからです。三身が一体に具わっているのが仏です。
『十地経論』に「一切の仏に三種の仏あり。一に応身仏、二に報身仏、三に法身仏なり」とありますように、全ての仏には三身が備わっています。ですから三身が別体の別教の仏は「実仏」には成り得ません。
仏は本来、色も形もない言葉を離れた真理なので、人間が認識できるものではありません。しかし人間が認識できず、人間と関係を持てなければ、人間を救うこともできません。ですから仏は、私たちの認識に乗る様々な姿を現わして法を説きます。それが法身・報身・応身といった仏の三身(法報応の三身)の現れ方です。
「法身」は、真理であり法そのものですから、人間が認識することができない仏であるのに対し、法を説くために人間が認識出来る姿で(人に応じて)出現された仏が「応身仏」であり、お釈迦さまです。
そのお釈迦さまの応身の姿にも「劣応身」と「勝応身」とがあり、実体に捕らわれた声聞や仏法をしらない凡夫達が住む「同居穢土」いわゆる娑婆世界に住する蔵教の教主たるお釈迦さまが「劣応身」です。
実体思想が強い「同居穢土」の住民は実体に即して法を説かないと理解に至りませんから実体(肉体)を備えた「劣応身」として仏が娑婆世界に出現されました。
しかし実体思想に捕らわれた声聞達は「析空」に堕ちいってひたすら解脱による「灰身滅智」の境地を目指します。この蔵教がひろく説かれた正法時代の前半の500年を「解脱堅固の500年」といいます。
それに対し実体思想から離れた空(体空)を悟った境涯に対しては仏は肉体を必要としません。「方便土」に住して神通力によって変現自在の仏身を示していきます。そのお釈迦さまの仏身が「勝応身」です。
通教で体空を展開していった竜樹が活躍したこの正法時代の後半の500年を「禅定時代の500年」といいます。
お釈迦様は蔵教がひろく説かれた「解脱堅固の500年」では「劣応身」として法を説き、通教が展開された「禅定時代の500年」では肉体から解脱して「勝応身」として法を説いていきました。
この解脱堅固、禅定時代というのは「五箇の五百歳」といいまして、釈迦滅後の二千五百年間を五期の五百年間に区切って、仏法流布の状態を説明したものです。
【五箇の五百歳と代表人物】
○ 釈尊滅後、はじめの五百年を解脱堅固 迦葉尊者・阿難尊者
戒律を中心に解脱を目指す小乗の教えが盛んだった時代
○ 次の五百年を禅定堅固(ぜんじょうけんご)
竜樹菩薩・天親菩薩
空思想がひろまり禅定が盛んに行われた時代
○ 次の五百年を読誦多聞堅固(どくじゅたもんけんご) 天台大師(智顗)
経文が中国に渡り、読誦や教義の研究論議が盛んに行われた時代
○ 次の五百年を多造塔寺堅固(たぞうとうじけんご) 伝教大師(最澄)
経文が日本に渡り、塔や寺が盛んに建造されていった時代
○ そして五番目の五百年は、闘諍堅固(とうじょうけんご) 日蓮大聖人
修行僧らが互いに自説を主張して譲らず、争いが盛んな時代
また、法報応の三身を図に示すと次のようになります。
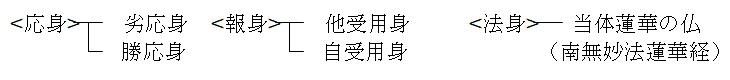
これらの図に蔵教・通教・別教・円教の四教と五箇の五百歳を重ねて図にまとめると次に示す<五箇の五百歳と四教の図>のようになります。
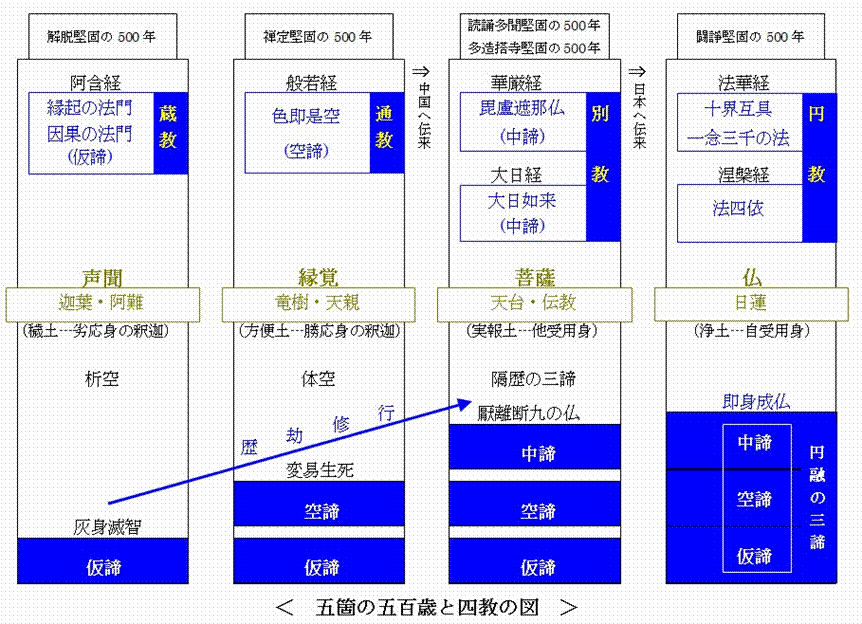
図に示すように蔵教で劣応身の釈迦が仮諦を説き、通教で肉体から解脱した勝応身の釈迦が変幻自在に「空」を説き、別教で衆生を涅槃へと導く仏、他受用身が顕されます。
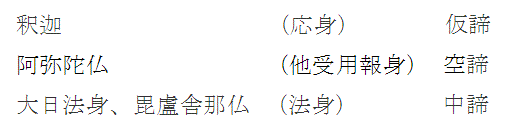
このように別教に至って三身が説き明かされた訳ですがここでの三身はそれぞれが別体として顕されています。それぞれが互いに相隔たったかたちで説かれているので「隔歴の三諦(きゃくりゃくのさんたい)」といいます。一身に三身を具えているのが仏ですから別教で説かれる別体の仏はみな権仏となります。
円教
蔵・通・別・円の四教の中で最後に位置する円教において法華経が説かれ、それまでは決して明かされることが無かった「十界互具」が初めて示されて一念三千の御法門が説き明かされます。
それによって今まで別体として説かれてきた応身・報身・法身が一身に顕され空・仮・中の三諦が円融します。
そのことが『三世諸仏総勘文教相廃立』(P.571)の中で示されています。
「損変易生とは同居土の極楽と方便土の極楽と実報土の極楽との三土に往生せる人・彼の土にて菩薩の道を修行して仏に成らんと欲するの間・因は移り果は易りて次第に進み昇り劫数を経て成仏の遠きを待つを変易の生死と云うなり、下位を捨つるを死と云い上位に進むをば生と云う是くの如く変易する生死は浄土の苦悩にて有るなり、爰に凡夫の我等が此の穢土に於て法華を修行すれば十界互具・法界一如なれば浄土の菩薩の変易の生は損じ仏道の行は増して変易の生死を一生の中に促めて仏道を成ず」
【解説】
「生死には「分段生死」と「変易生死」の二種があります。「分段生死」は凡夫の生死(六道輪廻)で、「変易生死」は五蘊を空じた聖者(声聞・縁覚・菩薩)の不可思議な生死をいいます。
声聞・縁覚・菩薩の各々が菩薩の道を修行して仏に成らんとする因を積んでいく中で、数えきれない程の劫数を経て同居土(穢土)から方便土へ、方便土から実報土へ下位を捨てて上位に転生(生まれ変わり)し遥か遠くの仏(厭離断九の仏)が住む浄土を目指すことを「変易の生死」といいます。しかし、穢土において凡夫が法華経を修行すれば十界は互具し、三身は一身に現れて「変易の生死」を一生の内に修めて即身成仏を遂げることができるのです。」
一念三千の法門はとても複雑で難解極まりない法門です。ですからお釈迦様は衆生が理解に至るように分かり易いところから徐々に法を説いていかれたのです。本来一仏乗の教えである法華経を三乗に開いて説き、最後に再び一つに集約されます。それが「開三顕一」の意味するところです。
法華経が説かれる以前の正法・像法時代の仏道修行は、<五箇の五百歳と四教の図 P.29>に示されるように声聞から縁覚そして菩薩へと次第に境涯を高め、気の遠くなるような歴劫修行の果てに最終的に九界の凡夫の身を滅して転生によって浄土へと向かう「変易の生死」でした。
末法の時代に生まれてきた私たちは、そのような大変な修行をしなくても大聖人様が顕して下さった「事の一念三千」である御本尊様に日夜朝暮に又懈らず「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えていくことで、隔歴の三諦である「変易の生死」を、円融の三諦として一生の内に修めていくことが出来ます。その三諦が円融する仕組みを次章「円融三諦」で詳しくお話ししてまいりたいと思います。
法華経 第一章 『 迹 門 』 完
令和元年 八月 十五日
法介
